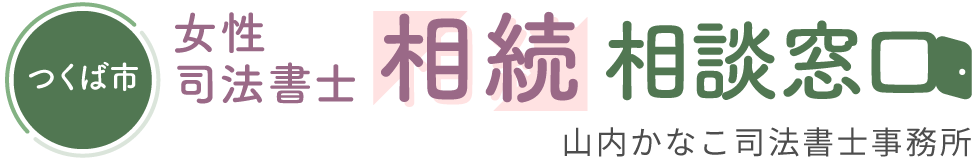つくば市で司法書士事務所を営む当事務所では、遺言書の作成に関するご相談を多数承っております。
遺言書は、相続トラブルを防ぐための有効な手段として注目されていますが、「どのように作成すればよいのかわからない」「本当に必要なのか」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこで本ページでは、遺言書を作成するメリットや種類、注意点などを初心者の方向けに解説いたします。
このページの目次
遺言書とは?作成するメリット
遺言書とは、財産の分配や相続に関する意思を法的に残すための書類です。
遺言書を作成する主なメリットを4つご紹介します。
1. 自分で遺産の分け方を決定できる
遺言を残すことで、誰にどの財産を遺したいのか決めることができます。
2. 相続人以外にも財産を渡すことができる
遺言がない場合、相続権があるのは法定相続人となります。
一方で遺言を残すことで、相続人以外の人にも財産を渡すことができます。内縁の妻や、寄付したい慈善団体にも財産を遺すことが可能です。
3. 相続人同士の争いを防ぐことができる
遺言は遺産の分割方法を決めるのみでなく、残された家族への想いやメッセージを記載することもできます。
どうしてこの分け方にしたのかという故人の想いや家族への感謝の気持ちを残しておくことで、相続人間のトラブル予防も期待できます。
4. 相続人の負担を軽減できる
相続人が複数いて遺言がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず、残念ながら意見の対立があると遺産分割協議がまとまらず「争族」になることがあります。
遺言があれば、原則として遺言の内容に従って遺産を分割できるため、相続人が集まって協議をする手間や精神的な負担を軽減できます。
遺言書の種類と特徴
遺言書には主に以下の3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。当事務所では安心して確実に想いを実現できる公正証書遺言の作成をお勧めしております。
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きで作成する形式です。最も簡単に作成できる遺言書ですが、いくつかの注意点があります。
特徴とメリット
- 手軽に作成でき、費用がかからない。
- 他人に内容を知られることなく、自分だけで作成可能。
デメリット
- 法律に定められた形式を守らないと無効になる可能性がある。
- 紛失や改ざんのリスクがある。
- 発見されにくい場合がある。
- 相続開始後に家庭裁判所で検認が必要
2020年の法改正により、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が開始されました。この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
作成時に証人が2人必要になりますが、司法書士が証人を手配することも可能です。
特徴とメリット
- 公証人が作成するため、形式不備による無効の心配がない。
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがない。
- 遺言書の内容が確実に実現される。
デメリット
- 公証役場への手続きが必要で、一定の費用がかかる。
- 公証人に内容を伝える必要があるため、プライバシーが気になる場合がある。
3. 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証人に証明してもらう方法です。遺言内容を公開したくない場合に有効ですが、形式に不備があると無効になるリスクがあります。
特徴とメリット
- 遺言の内容を秘密にできる
デメリット
- 公証役場への手続きが必要で、一定の費用がかかる。
- 内容について公証人が関与するわけではないので、無効になる可能性がある。
- 相続開始後、開封前に家庭裁判所の検認が必要
遺言書作成のタイミング
遺言書は、何度でも書き直し可能であり、撤回することもできます。そのため、「作成しようか迷っている」という方も、まずは一度作成してみることをおすすめします。以下のようなタイミングで作成を検討すると良いでしょう。
- 結婚や離婚をしたとき(特に事実婚の場合は注意が必要です)
- 子どもが生まれたとき(子どもが未成年の場合、遺言がないと特別代理人の選任が必要になることもあります)
- 財産を購入したとき(不動産や高額な資産など)
- 大きな病気や高齢になったとき
遺言書は、早めに作成しておくことで安心感を得られるだけでなく、状況が変化した際に適宜見直すこともできます。
こういう方に作成をおすすめ
「自分には関係ない」と思っている方も、以下に該当する場合は遺言書の作成を強くお勧めします。
1. 子どもがいない夫婦の場合
相続する優先順位は法律により決められています。
配偶者:常に相続人となります。
第一順位 子ども
第二順位 直系尊属(父母や祖父母)
第三順位 兄弟姉妹
子どもがいない夫婦の場合は、遺言がない場合配偶者の家族と遺産分割協議をする必要があります。残された配偶者に手間や精神的に大きな負担がかかるだけでなく、遺産分割協議が揉めると自宅や財産を希望通りに遺してあげられないこともあります。
残された配偶者が安心して生活できるように遺言書の作成は必須です。
2. 事実婚のパートナーがいる場合
法律上、事実婚のパートナーは法定相続人に含まれないため、遺言書がなければパートナーに財産を残すことができません。遺言書を作成することで、事実婚のパートナーに財産を遺贈したり、生活を支えるための配慮をすることが可能です。
3. 子どもが未成年の場合
未成年の相続人は遺産分割協議に参加できません。親と子の利益が相反する場合、親は子に代わって遺産分割協議をすることもできません。
そのため、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要になり、協議内容にも制限がかかることがあります。
遺言があれば面倒な手続きを踏むことなく、スムーズに財産を分配することができます。
4. 特定の人に財産を渡したい場合
例えば、特定の相続人に多めに財産を分けたい場合や、家を守るために長男だけに不動産を相続させたい場合など、遺言書によって希望を反映させることができます。
5. 再婚していて前配偶者との間に子供がいる場合
離婚した夫婦の間に子どもがいた場合、その子には相続権が発生します。
しかし、夫婦が離婚した場合、親権を持たない元配偶者の場合には、子どもと疎遠になってしまうことも少なくありません。そのような場合に遺言がないと、相続手続きを進めるには前配偶者の子と現配偶者との間で遺産分割協議が必要になり、手続きが複雑になったり、協議がうまく進まないことも考えられます。
遺言書を作成しておくことで、遺産分割の方針を明確に示し、家族間の争いを未然に防ぐことで大切な家族を守ることができます。
遺言書作成の流れと注意点
遺言書を作成する際には、以下の流れに沿って進めるのが一般的です。
1. 財産の洗い出し
まずは、自分が所有している財産をリストアップしましょう。不動産や預貯金だけでなく、株式や生命保険、貴金属、借金なども含めて明確にしておくことが重要です。

2. 相続人の確認
次に、法定相続人を確認します。配偶者や子どもだけでなく、親や兄弟姉妹などが相続人になる場合もあります。事実婚のパートナーや養子などの状況に応じて、専門家に相談することをおすすめします。

3. 遺言書の種類の選択
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれが適しているかを考えましょう。不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することで、安心して進めることができます。

4. 遺言書の作成と保管
作成した遺言書は、紛失や改ざんを防ぐために適切に保管する必要があります。法務局の保管制度や信頼できる第三者への預け入れを活用すると良いでしょう。
- 形式不備を避ける
遺言書は形式が非常に重要です。不備があると無効になるリスクがあるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。 - 定期的な見直し
状況が変化した場合は、遺言書の内容を見直し、必要に応じて更新しましょう。
司法書士に相談するメリット
遺言書の作成には、法律や手続きに関する専門知識が必要です。司法書士に相談することで、以下のようなメリットを得られます。
1. 適切なアドバイスが受けられる
遺言書に記載すべき内容は人それぞれ異なります。
たとえば、財産の内容や家族構成によって、最適な遺言書の種類や内容が異なります。司法書士は、依頼者様の状況を詳しくヒアリングし、最適な方法を提案します。
2. 法的に有効な遺言書を作成できる
司法書士は、法律の専門知識を活かして、法的に有効な遺言書を作成するサポートを行います。
不備がない遺言書を作成することで、相続手続きがスムーズに進むだけでなく、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
3. 手続きがスムーズに進む
特に公正証書遺言を作成する場合、公証役場での手続きが必要です。司法書士に依頼すれば、必要書類の準備や手続きをスムーズに進めることが可能です。
4. 負担を軽減できる
遺言書の作成や手続きに慣れていない方にとって、内容を考えたり書式を整えたりするのは大きな負担となりがちです。
司法書士に依頼することで、その負担を軽減し、安心して遺言書を作成することができます。
まとめ
遺言書の作成は、将来の安心を得るための大切なステップです。
茨城県つくば市にお住まいの方で、「遺言書の作成方法や手続きに不安がある」「どの種類を選べばよいのかわからない」とお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。司法書士が丁寧に解説し、一人ひとりの状況に合わせたサポートを行います。
遺言書の作成は、何度でも書き直し可能であり、撤回することもできます。迷っている方も、まずは一度お気軽にご相談ください。
遺言書は、家族や大切な方への思いやりを形にするものです。司法書士のサポートを通じて、安心できる未来を一緒に築いていきましょう。