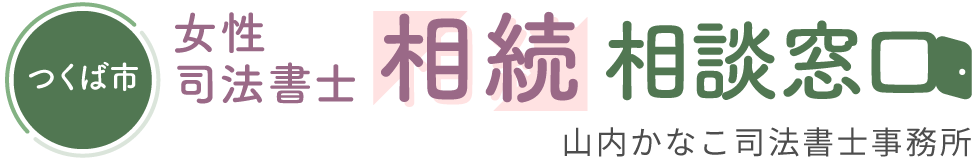相続登記による名義変更を行う際には、さまざまな書類を準備する必要があります。「どの書類が必要なのか」「どこで取得できるのか」といった疑問を持つ方も多いと思いますので、ここでは遺産分割協議による相続登記を申請する場合の必要書類を具体的に説明します。
加えて、それぞれの書類に関する注意点や取得方法も解説します。
このページの目次
被相続人(亡くなった方)に関する書類
まず、相続登記では被相続人に関する情報を正確に確認するための書類が必要です。以下がその主な例です。
1. 戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃える必要があります。これは、相続人を確定するための重要な書類です。
取得方法
被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。本籍地が複数回変更されている場合、それぞれの役所から取り寄せる必要があります。
2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも、戸籍謄本・除籍謄本を請求できるようになりました。ただし、この広域交付の請求ができる方には制限があります。また、役所窓口にて顔写真付きの本人確認書類の確認が求められるなど取得に条件がありますのでご注意ください。
古い戸籍は「改製原戸籍」や「除籍謄本」と呼ばれる場合があります。これらも含めて、すべて取得してください。
2. 住民票の除票または戸籍の附票
被相続人の最後の住所を証明する書類です。
登記簿に記録されている名義人の住所と、被相続人の本籍・住所との繋がりを確認し、登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明するために必要となります。
【住民票の除票】取得方法
被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得できます。
本籍地の記載ありでご取得ください。
地域によっては保管期間が過ぎている場合があるため、早めに取得してく ださい。
【戸籍の附票】取得方法
被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で取得できます。
本籍地の記載ありでご取得ください。
地域によっては保管期間が過ぎている場合があるため、早めに取得してください。
相続人に関する書類
相続人が誰であるかを証明するための書類も必要です。
これには以下のようなものがあります。
1. 戸籍謄本(相続人全員分)
相続人であることを証明するために、相続人全員分の戸籍謄本を準備します。
取得方法
相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
結婚や離婚により本籍地が変更されている場合、変更後の本籍地の役所で取得する必要があります。
条件により、本籍地以外の役場の窓口やコンビニでも取得できる場合がありますのでご活用ください。
2. 印鑑証明書(相続人全員分)
相続登記に必要な書類の一つである遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印することが必要です。そのため、相続人全員分の印鑑証明書が必要となります。
取得方法
相続人が住民登録している市区町村役場で取得できます。
法務局以外の相続手続きに使用する際には、印鑑証明書は発行からの有効期限が必要とされる場合があります。
3. 住民票(不動産を相続する方)
不動産の新しい名義人となる方の住所を証明するための書類です。
不動産に関する書類
相続する不動産についての情報を特定するために、以下の書類が必要です。
1. 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
不動産の評価額を証明するための書類です。相続登記では登録免許税(登記申請する際に納付する印紙代)を計算する際に使用します。
取得方法
不動産が所在する市区町村役場の税務課または都税事務所で取得可能です。
最新の年度のものを取得してください。また、不動産が複数ある場合、それぞれの不動産について取得する必要があります。
2. 登記簿謄本または登記事項証明書
不動産の権利関係を確認するための書類です。法務局で取得することができます。
取得方法
全国の法務局で取得可能です。
最新の情報を反映したものを用意してください。
遺産分割協議書(必要に応じて)
相続人が複数いる場合は、遺産の分け方について相続人全員で合意した内容を記載した「遺産分割協議書」が必要です。
| 内容 | 協議書には、不動産や預貯金などの遺産について、どの相続人が何を取得するかを明記します。 |
| 記載事項 | 相続人全員の署名と実印が必要です。 |
| 作成方法 | 遺産分割協議書の作成は、形式や記載内容に不備があると無効になる可能性があります。専門家に相談しながら作成することをおすすめします。 |
相続人全員の同意が得られない場合は、遺産分割協議書を作成することができません。この場合、家庭裁判所で調停や審判を行う必要がある場合もあります。
その他の必要書類(ケースに応じて)
以下の書類は、特定の条件に該当する場合に必要となります。自身の状況に応じて、必要な書類を確認してください。
1. 遺言書
被相続人が生前に遺言書を作成している場合、その内容に基づいて手続きを進めます。
遺言書が公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言でない場合、家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。検認とは、検認日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
2. 相続放棄申述受理証明書
相続人の中に相続を放棄した方がいる場合、この証明書が必要です。
取得方法
相続放棄を行った家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)で取得できます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きを行う必要があります。
3. 相続人の中に亡くなられた方がいる場合の書類
相続人の中に亡くなっている方がいる場合、その方の戸籍についても出生から死亡まですべての戸籍が必要になる場合があります。
書類準備の注意点
相続登記や名義変更の必要書類は種類が多く、それぞれ取得先や手続き方法が異なります。
以下の点に注意して書類準備を進めましょう。
1. 書類の不備を防ぐ
必要書類に一部でも不備があると、手続きが遅れる原因となります。漏れのないよう確認しましょう。
2. 書類の取得先を確認する
書類によって取得先が異なるため、事前に確認しておきましょう。たとえば、戸籍謄本は市区町村役場、固定資産評価証明書は税務課、登記事項証明書は法務局で取得します。
3. 必要に応じて専門家に依頼する
相続登記に慣れていない方がすべての書類を揃えるのは大変です。
当事務所では必要書類の収集から作成、登記申請に至るまで代行することが可能です。ご依頼者様が煩雑な手続きに悩むことがないようにサポートいたします。
まとめ
相続登記による名義変更の手続きに必要な書類は多岐にわたりますが、一つひとつ確実に準備することで、手続きをスムーズに進めることができます。不備や漏れを防ぎたい場合は、司法書士に相談するのも有効な方法です。
茨城県つくば市にある当事務所では、相続登記による名義変更の書類準備から手続き代行まで、トータルでサポートいたします。「どの書類が必要なのかわからない」「自分で準備するのが不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。